最近AVIOTのピヤホン8(TE-W1-PNK)を購入しました。
以前はAnkerのSoundcore Space A40という1万円くらいのワイヤレスイヤホンを使用しており、価格的には1.5倍から2倍くらいのグレードアップということになるのですが、ピヤホン8の音質に非常に満足しています。
Bluetoothイヤホンで音楽を聴く場合の音質を決める要素は大きく3つあります。

- 再生する音楽データの品質
- 再生された音をスマホ等からイヤホンに届ける際の圧縮データの種類
- イヤホン自体の音を鳴らす能力
1から3の、言い換えれば上流から下流まで劣化がなければそればベストですが、これらのどれかの品質が悪ければ、最終的に耳に届く音は原音とは大きく異なる音になってしまいます。
近年は多くの人が音楽配信のサブスクリプションサービスで音楽を聴いていると思いますので、1.音楽データに関しては一部のハイレゾ配信を除き圧縮音源を聞くことになります。その品質は配信サービスごとに異なり、また再生アプリの設定でも変化します。再生アプリ上で最高音質を選択したとしても、非可逆圧縮をしている以上は劣化は避けられません。ですが今回はこの劣化に関しては目をつぶることにします。
2.コーデックは一旦飛ばして、3はイヤホン自体の話です。現在の私の場合はピヤホン8が本当に良いイヤホンだと思っているのですが、それよりも性能が良いイヤホンはたくさんありますし、よりコスパの良いイヤホンもたくさんあります。メーカーやモデルごとのチューニングがあり、人それぞれ好みが異なりますので、私は「絶対にピヤホン8を買え」とは言えません。
さて、本題は2番目、Bluetoothの圧縮形式(コーデック)です。

コーデック(圧縮形式)は、音のデータをコンパクトにするアルゴリズムのことです。
Bluetoothは電波通信の規格の一つです。Bluetoothイヤホンでは音のデータをBluetoothの電波に乗せてイヤホンに転送しますが、Bluetoothの電波で送ることができる情報量には限りがあります。また電波である以上、混雑する場所や電波ノイズが多い場所では通信が途切れることが想定されます。そうなると音が途切れて音飛びが発生してしまいますが、それを防ぐためにはデータはできるだけ小さくして、余裕を持ってデータを転送することが理想的です。
現在販売されているワイヤレスイヤホンの多くはSBCは必ず対応していて、それに加えてAAC、aptX、LDACのいずれかが対応しているケースがほとんどだと思います。さらに言うと「SBC、AAC、LDAC対応」という機種が多いような気がします。この3つでは音質はどのように違うのかを、私の個人的な感覚で比較し、解説していきたいと思います。
仕様の違い
SBC、AAC、LDACの仕様の違いは以下の通りです。
| SBC | AAC | LDAC | |
|---|---|---|---|
| 最大サンプリングレート | 48 kHz – 16 bit | 48 kHz – 16 bit | 96 kHz – 24 bit (32 bit) |
| 最大ビットレート | 328 kbps (345 kbps) | 256 kbps (320 kbps) | 990 kbps |
| 対応モバイル機器 | iOS, Android | iOS, Android | Androidのみ |
| 特徴 | 標準コーデックであり、あらゆるBluetoothイヤホンでサポートされる。 音質は悪く、遅延も大きい。 接続は安定している。 | SBCよりも優れた音質。 対応機器は非常に多い。 接続は安定している。 | ソニーが開発したハイレゾ対応コーデック。 iPhoneは非対応。 高ビットレート設定では接続が不安定。660kbpsや 330kbpsでは安定する。 |
音質という点ではSBCが最も劣ります。音質の比較として土俵に上がってくるのはAACとLDACです。
AACとLDACはサンプリングレート、ビット数、圧縮アルゴリズム、ビットレートが異なります。
| サンプリングレート | 音の波形を記録する1秒当たりの回数。単位はHz。 |
| ビット数 | 音の波形の強さを記録する細かさ。2n 段階。単位はbit。 |
| 圧縮アルゴリズム | 大きな音声データを小さいデータに変換する計算手順。今回の話ではAACやLDACが圧縮アルゴリズム(コーデック)。 |
| ビットレート | 圧縮したデータの1秒間当たりのサイズ。単位はkbps。 |
前提として、音は滑らかな波形の波でできています。この滑らかな波形をデジタルデータに変換するには、時間方向と大きさ方向に有限の段階で区切って記録することになります。時間方向の区切り方がサンプリングレート、大きさ方向の区切り方がビット数で表されます。
サンプリングレートとは、アナログ波形をどれくらい細かくデータに記録するかというものです。空気の波である音は電気的なアナログ波形に姿を変えるわけですが、そのアナログ波形を非常に短い時間で区切り、電圧として記録していくことでデジタルデータに変換します。48 kHz (48000 Hz)は、音の波形を1秒間あたり4万8000分割して、その1サンプル(1/48000秒間)の波の大きさを電気に変換して、繰り返し記録していきます。96 kHzの場合は9万6千分割、1サンプルは1/96000秒間。非常に細かくデータを記録します。元の音の波形をより忠実に再現しようとした場合、このサンプリングレートは多いほうが良いです。
ビット数はその電圧値をどれくらいの精度で記録するかというものです。デジタルデータは数値を2進数(0と1)で表現しますが、ビット数はその2進数の桁数のことです。16ビットでは16桁、32ビットでは32桁で、表現できる範囲はそれぞれ216と232です。音をデジタルデータにするには、音の大きさを有限の数の段階に変換します。これを216段階や232段階に変換して記録し、この記録を1秒間に4万8000回繰り返す、という形でできています。
サンプリングレートとビット数が大きい場合、音楽のもとの波形をより忠実に再現できます。
サンプリングレートとビット数が小さい場合、音の波形の細かい形状が再現できません。
AACとLDACでは、LDACのほうが仕様上は元の波形を忠実に再現する能力を持っています。
音の波形の細かい形状を再現するため、データ量は大きくなります。LDACのビットレートが大きいのはそのためです。圧縮アルゴリズムが異なるためビットレートの大小で単純比較はできませんが、LDACのほうがより多くの情報を持っているということは言えると思います。
音の違い
ではAACとLDACの音の違いを評価していきますが、まず前提として、音の聞こえ方は人それぞれです。耳に入ってきた空気の振動を脳が音として認識しますが、耳の性能は人それぞれ、脳が認識できる音も人それぞれです。あくまで私個人の感覚で評価していきます。
AACは ”聞きやすい音” になります。高音成分のキラキラした感じがマイルドになり、多数の楽器が鳴っているシーンでもそれらがいい感じにまとめられ、歌ものであればボーカルが聞きやすくなります。圧縮音源にありがちなシンバルの高音などがグシャグシャに崩壊しているような劣化はあまりないため、聞いていて不快になるようなことはありません。
LDACはあらゆる音がクリアに鳴っています。LDACとAACを交互に聞くと、AACは少し薄暗くて狭い空間で鳴っている感じ、LDACはクリアな空間で横の広がりや空間の奥行きを感じられます。ボーカルの息遣いやギター・ベースアンプの空気感、打楽器のアタック感など、アーティストやエンジニアが作り上げた音を感じられます。これは楽器経験がある人や生演奏を楽しむ習慣がある人にとっては嬉しい音ですが、デメリットとして音の情報量が多すぎて聞き疲れしやすいことやボーカルに集中できないといったことが挙げられると思います。
またLDACで驚いたこととして、YouTubeMusicの配信音源でも明確に上記の違いを感じました。YouTubeMusicの配信音源は圧縮音源なので、元々の音がある程度の劣化をしています。CDやハイレゾの可逆圧縮(劣化がない圧縮)の音を聞いて上記の違いが出るのであればそれはそれで納得ですが、YouTubeMusicの音は最高音質設定でも圧縮されているため、下の図で言うと1.音楽データが既に劣化しているのです。

上流のほうで音が劣化しているにもかかわらず、2.コーデックの違いで上記のような明確な違いを感じられました。ここから考えられることは、1.音楽データの品質は元々それなりに良くて、それを2.コーデックで圧縮する際にAACでは大きく劣化してしまうのに対し、LDACは劣化を極限まで抑えているということです。
もちろん大前提として、3.イヤホンの品質が高くないと、上記の違いは分かりません。逆に言うと、3.イヤホンが安くて質も良くないという場合は1.音楽データや2.コーデックがどんな条件でも同じように聞こえるということです。
使用感の違い
音質以外の部分での違いを解説していきます。
| AAC | LDAC | |
|---|---|---|
| イヤホンの電池持ち | 長い | 短い |
| 接続の安定性 | 良い | 悪い(高ビットレートで音質重視) 良い(ビットレートを抑えて安定性重視) |
| 対応しているイヤホンの種類 | 多い(ほぼ全てのBluetoothイヤホンで使用可能) | 少ない(安いイヤホンや古いイヤホンでは非対応) |
| 対応しているスマートフォン | iPhone, Android | Androidのみ |
イヤホンの電池持ちはAACのほうが長いです。ピヤホン8にはデータがないのでAnker Soundcore Space A40から引用しますが、イヤホン本体の電池持ちがAACやSBCで最大10時間なのに対し、LDACでは最大6時間となっています。これはLDACのデータ処理が重いことが考えられます。ビット数やビットレートが大きいことは、必然的に大量のデータを処理することになります。電池持ちが短くなるのは当然と言えば当然です。長時間の使用を考えているならAACを使うべきかもしれません。
接続の安定性はAACが安定しています。LDACもビットレート設定次第ですが、高ビットレート設定では音飛びが激しい場合があります。聞けたもんじゃありません。自宅の室内でも不安定なので、電車の中や人通りが多い場所での使用は絶望的でしょう。中ビットレートや低ビットレート設定が現実的だと思われますが、せっかくのLDACで音質を重視したいのに、ビットレート設定を妥協してしまうのはもったいない。。。 このビットレート設定と安定性の関係はイヤホン本体の性能やスマートフォンの性能によっても変わるかもしれません。少なくとも、ピヤホン8で高ビットレート設定を使用することは難しそうです。なお、LDACのビットレート設定はデフォルトではベストエフォートになっているはずです。接続の安定性と音質を両立するベストな設定が自動的に選択されます。
対応しているイヤホンの種類はAACが圧倒的に多いです。LDACはハイレゾ対応機種に搭載される傾向にあります。
対応しているスマートフォンはiPhoneではAACのみ対応なのに対して、AndroidはAACもLDACも使用できます。
まとめ
AACとLDACの聞き比べをして感じたことや、使用感の違いをまとめました。
音楽を聴く際に何を優先するかは人によって違います。より良い音で聴きたい、楽器や歌声の細かい表現を感じたいという方は、ハイレゾ対応の高価なイヤホンをLDACで使うことをお勧めします。しかし、LDACを全員使うべきとは考えません。ボーカルを集中して聴きたい場合やとにかく気軽に聴きたい場合などはむしろAACのほうが適しているかもしれません。
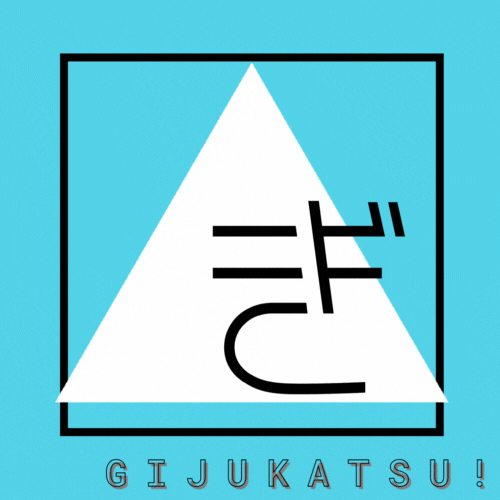

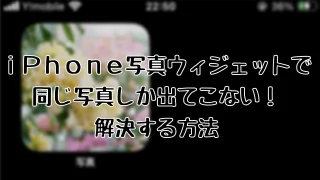
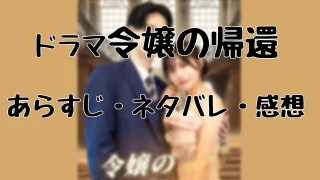
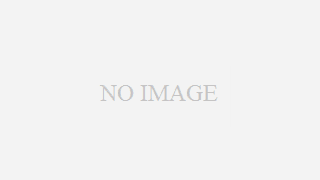
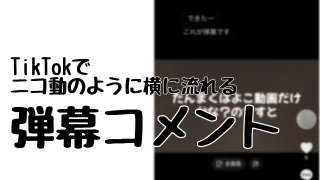

コメント